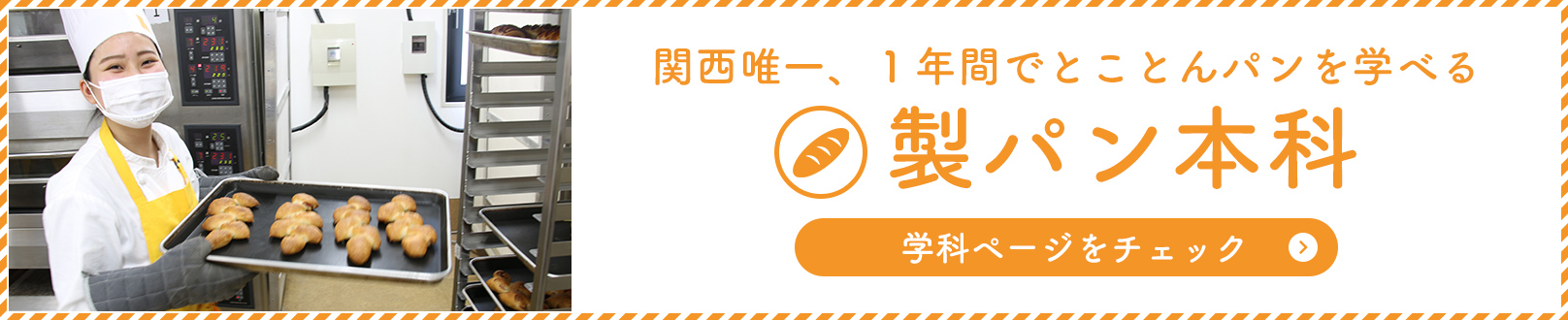バゲットやカンパーニュなど、自宅で本格的なパンを作る方も増えています。
これらのパンの種類は「高加水パン」と呼ばれるのをご存知でしょうか?
高加水パンは水分を多く含むパンのことですが、水分量によってパンの仕上がりが変わってきます。
この記事では、高加水パンの生地の特徴や失敗したときの対処法なども紹介しているので参考にしてください。
高加水パンとは一体何?加水率によって生地が変わる


高加水パンとはその名の通り、水分を多く含んだパンのことです。
加水率は粉の総重量を100%とした場合、粉量に対する水分量となります。
水分量によってパンの種類も変わってくるので、それぞれの加水率を知っておくと良いでしょう。
加水率60%未満は噛みごたえが出る
加水率60%未満は水分が少なく、噛みごたえのある生地になります。水分が少ない分、生地が固いのでこねるのに力が必要です。
焼き上がりはベーグルのように目が詰まっており、硬く感じられるでしょう。
加水率65%前後はふんわり感が出る
加水率65%前後は、食パンや菓子パンを作る際の一般的な水分量です。
焼き上がりがふんわりとしており、生地のキメが細かく伸びやすくなります。
加水率70〜80%はベタつき感が出る
加水率が70〜80%の場合は、高加水パンと呼ばれる水分量です。
フランスパンやカンパーニュなどのパンを高加水パンと呼んでいます。
焼き上がりは生地に大きな気泡ができ、少しベタつきもあるのが特徴です。
水分量が多いので生地をまとめにくく、他のパンよりも高度な技術が必要となります。
高加水パン生地の特徴|メリットとデメリット


高加水パンは高温で短い時間で焼き上げるため、表面がこんがりとして硬く、中はしっとりしているのが特徴です。
調理法で例えるならベーグルがウェルダン、食パンがミディアム、バゲットがレアというようなイメージです。
高加水パンのメリット
高加水パンを作ったり食べたりする際のメリットを見ていきましょう。
小麦粉の良さを活かせる
生地を発酵させて膨らませる「酵母」は、パン作りに欠かせないものですが、高加水パンの場合は他のパンよりも酵母を少なくして低温長時間発酵させるのが特徴です。
また、低温長時間発酵させることで酵母の独特な香りもなくなり、小麦の風味が引き立ちます。
賞味期限が長くなる
高加水パンのような水分率の高いパンを焼くことででんぷんが糊化し、内側に水分を保持する効果が出ます。
外側が硬いので水分が抜けにくく、日持ちして賞味期限が長くなるのです。
高加水パンのデメリット
高加水パンは食べることに関してメリットが多い反面、作る工程が難しいといわれています。
ベタついて作業時間がかかる
加水率の高い生地はゆるくてベタベタしており、手につきやすく扱いづらいのがデメリットです。
さらに高加水パンは流動性があるため、形を整えても平らになり、同じ形になってしまいやすいところもあります。
カビが生える場合もある
水分が多いとパンの傷みは抑えられますが、カビが生えやすくなります。
そのため、高温多湿を避けて保存しなくてはなりません。
夏場は特に注意が必要です。
高加水パンを作る方法や失敗したときの対処法


高加水パンを作るときは、加水率を計算しましょう。
ここでは高加水パンを作るときの加水率の計算や失敗しない対処法を紹介します。
加水率を計算する方法
加水率を計算する方法は以下の通りです。
(材料の水分量) ÷ (粉量) × 100=加水率
例えば200gの小麦粉に160gの水を加える場合の水分量を上記の計算に当てはめると
(材料の水分量160g) ÷ (粉量200g) × 100=加水率は80%
となります。
ただし、食パンなど卵や生クリームなどの副材料を使用する場合は、これらも水分量として考えなくてはなりません。
オーバーナイト法なら失敗しにくい
高加水パンで生地がまとまらず失敗したと感じたら、オーバーナイト法を試してみましょう。
オーバーナイト法とはこねた生地を冷蔵庫などの低温でゆっくり発酵させ、翌日以降に焼き上げる製法です。
オーバーナイト法は以下のようなメリットがあります。
- 生地は寝かせてる間に発酵するためしっかりこねなくても良い
- 2日間の工程に分けるので時間がなくても作れる
オーバーナイト法なら初心者でも高加水パンが上手く作れるはずです。
まとめ


高加水パンの特徴やメリット、加水率の計算法などについて解説してきました。
高加水パンはもちもちした食感が美味しく、噛めば噛むほど味わいが深くなります。
「もっとパンについて知りたい」「いろいろな高加水パンに挑戦したい」という方は製パンの専門学校で学ぶのもおすすめです。
神戸製菓専門学校は神戸「三宮駅」から徒歩で通える好アクセスな場所にあります。
製パン本科では、たった1年で基礎技術の反復練習や160種類以上のレシピなどで実践力を身につけられますよ。
1年のうち84%が実習中心のカリキュラムとなっており、実習量も圧倒的。
少しでも気になった方は、まずは気軽に無料のオープンキャンパスや資料請求を利用してみてはいかがでしょうか。