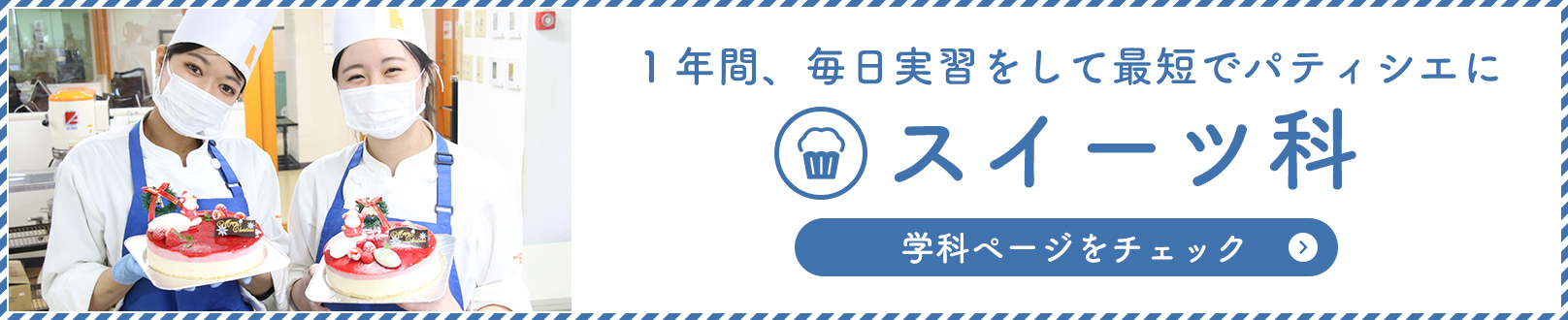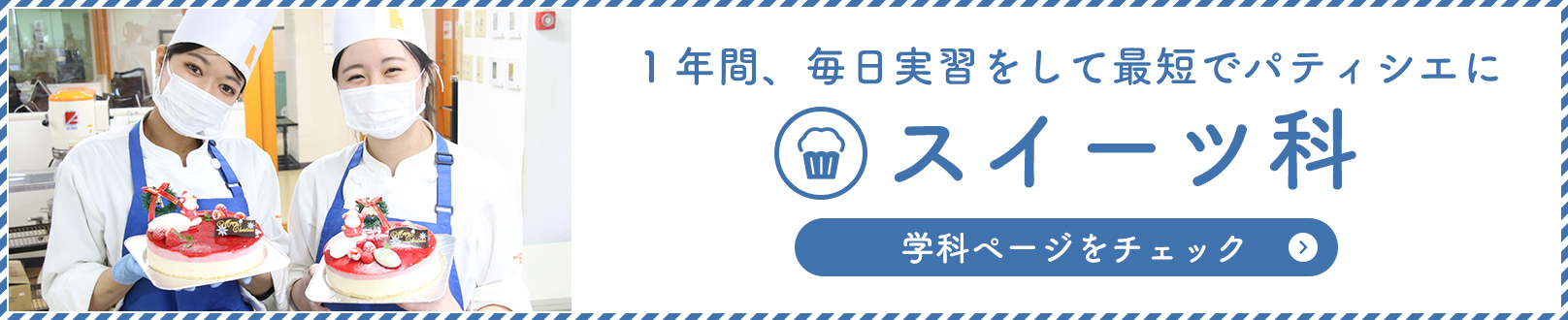スイーツや飲料水などの食品は、商品開発によって世の中に送り出されます。
そのためメーカーにとって商品開発は、自社の売り上げを伸ばすための重要な職種。
今回は、食品メーカーにおける商品開発の仕事を詳しくご紹介します。
人々の食生活を支える商品開発は、やりがいが大きく人気のある仕事です。
食品メーカーでの商品開発の仕事に興味がある人は、ぜひこちらの記事を参考にしてみてください。
食品メーカーにおける商品開発とは
食品は、生きる上で欠かせない身近で重要な商品。
人を笑顔にしたり人生を豊かにするなどの役割を持ち、多くの人の生活基盤を支えています。
食品メーカーにおける商品開発は、「誰をターゲットとするか」や「どうやって人を笑顔にするか」などのアイデアやイメージを商品化する仕事。
商品を実用化させるために、消費者のニーズや世の中の動きを踏まえながら試作を繰り返します。
ところが商品開発は人々の食生活を支えるというやりがいも大きい一方で、法規制が厳しく安全性の確保や品質の高さなど、越えなければならないハードルも多くあるのが現状。
特に飽食の日本では、栄養素や味以外にも楽しさ・驚きといった付加価値で過去の商品や他社と差別化することが求められています。
また技術的に実現できるか、採算は取れるかなどの視点も欠かせないため、業務の幅が広いのが特徴です。
だからこそ自分が開発した商品がヒットすれば、それだけ喜びは大きいと言えるでしょう。
食品メーカーでの商品開発の流れ


ここでは、商品開発の具体的な仕事内容について詳しく説明します。
商品企画
商品を開発するには、まず企画を立てる必要があります。
そこで重要になるのが情報収集。
商品を企画するためには日常生活で常にアンテナを張り、世の中の動向や消費者ニーズを把握することが不可欠です。
具体的に調査するのは、国内外でどのような商品が受け入れられ、どのような商品が求められているのかということ。
消費者アンケートや街頭インタビュー、他社の商品分析、食べ歩きなどを通して調査を行います。
華やかなイメージのある商品開発ですが、ヒット商品が生まれる背景には情報収集や分析といった地道な作業が欠かせません。
商品施策
情報収集の結果、開発したい商品が明確になれば商品施策を行います。
商品施策で重要なのは、自分が作りたい商品を作るのではなく開発する商品が利益を生み出せるかどうかという視点を持つこと。
「市場のニーズに合うか」「消費者に求められているか」「他社で類似商品はないか」といった点を考慮する必要があります。
さらに、特許や著作権を侵害しないように注意するのも重要なポイントです。
それらを踏まえたうえで、具体的にターゲットやコンセプト、デザインといった商品の仕様を企画書として作成。
プレゼンテーションで経営層や製造部門などに商品の魅力を伝えます。
会社として承認されなければ、どれほど良い商品であっても実用化することは不可能です。
そのため、製造コストや販売コストなども明示しなければならない重要な情報の1つ。
プレゼンテーションでは、経営層や製造部門などさまざまな視点で商品の魅力を的確に伝えることが求められます。
製造
商品化が決定したら、開発部門や製造部門と打ち合わせを行い、製造の工程に移ります。
試作品の完成時期や製造ラインの設備確認、人員の調整などの細かいスケジュールのほか、商品の原価などコスト面も考慮。
製造の工程では商品開発部門が中心となり、具体的に商品化までの調整を担当します。
その後
商品を売り出すためには、販売や広告の戦略も欠かせません。
消費者に魅力が伝わらなければ、良い商品であっても売り上げを伸ばすことはできないからです。
そこで商品化に成功したあとは、SNSやインターネットなどで話題性を高めるのも重要なポイント。
会社によっては営業部門が担当することもありますが、商品開発が広告の手配や販売ルートの確保、販売方法の検討を行うこともあります。
PRの機会が増えるほど多くの消費者の目に留まりやすくなるため、商品をヒットさせるためには販売・広告にも工夫が必要です。
食品の商品開発に求められる能力
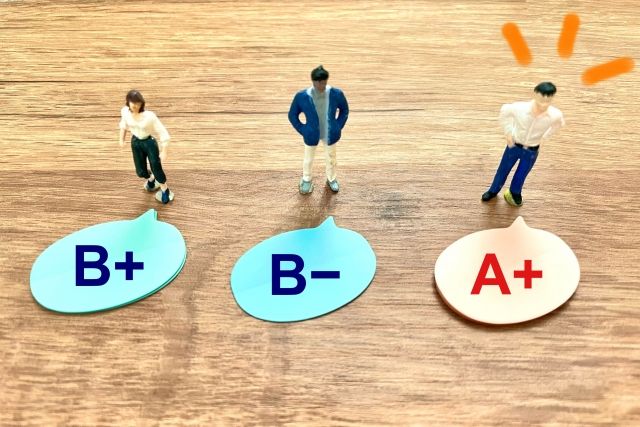
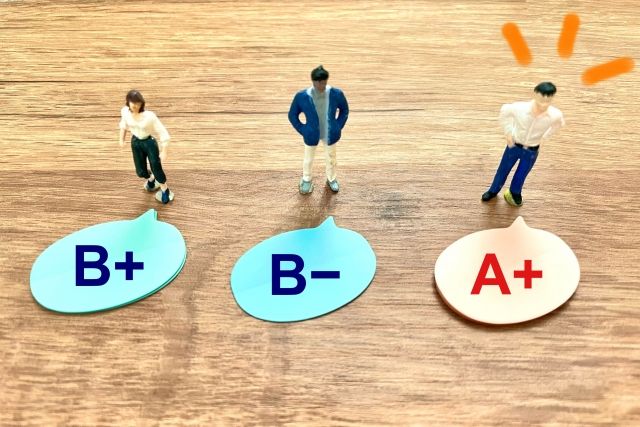
食品の商品開発に求められる能力は、主に3つです。
コミュニケーション能力
社内外でさまざまな人と関わる商品開発は、各所と連携しながら仕事を進める必要があります。
中には相手の立場に配慮しつつ、自分の考えや意見を通すべき場面も。
相手に不快感を与えず意見を伝えるには、適した立ち振る舞いや高いコミュニケーション能力が欠かせません。
コミュニケーション能力は円滑に仕事を進めるために重要な能力の1つです。
プレゼンテーションスキル
頭の中で描いたアイディアを経営層や製造部門へ伝える際には、プレゼンテーションスキルも大切。
商品化のメリットなど説得力があるかどうかによって、採用可否が決まります。
商品がヒットする根拠を、相手の心に響く表現でわかりやすく伝えることがプレゼンテーションを成功させるコツです。
プレゼンテーションを成功させなければ商品化はできないため、商品開発には必要なスキルと言えるでしょう。
デザインツールの操作スキル
商品のデザインを行う際は、IllustratorやPhotoshopといった画像編集ソフトを使用します。
このスキルを持っていると、商品のイメージをわかりやすく相手に伝えることが可能。
業務を円滑に進めるためにも、デザインツールの操作スキルを身につけておくと役に立ちます。
食品の商品開発に携わるには?
では食品の商品開発に携わるには、どのような方法があるのでしょうか。
商品開発部署に応募する
商品開発の求人を出している食品メーカーに応募し、就職する方法です。
商品開発は食品メーカーでは欠かせない部署。
希望とマッチする求人も多く見つかるでしょう。
場合によっては販売や営業といった経験を積まなければ商品開発に携われないこともありますが、既存商品への知識を深めることも大切な業務。
就職先の企業で希望しない職種に配属されたとしても、いずれ商品開発に携わるために必要なステップとして前向きに捉えましょう。
部署異動を利用する
商品開発の部署がある企業に勤めている場合は、部署異動の制度を利用しましょう。
特に現職の仕事が評価されているのであれば、スムーズに部署異動が実現できるはずです。
転職など大きく環境を変える必要がないのが、部署異動のメリット。
ただし異動制度は企業によって異なるため、人事担当者に問い合わせるなどで制度の詳細を確認しておく必要があるでしょう。
専門学校を卒業する
食品メーカーの商品開発に就職を希望するのなら、専門学校を卒業するのもおすすめです。
「神戸製菓専門学校」の製菓本科は、商品開発を目指すためのカリキュラムが充実しています。
中でも専門性を究めるための製菓研究ゼミが特徴。
自分たちでテーマを決めて1からオリジナルのお菓子を企画します。
将来食品メーカーで商品開発に携わる際に有用な経験となるでしょう。
まとめ
神戸製菓専門学校には、食品メーカーの商品開発に携わりたい人に適したゼミや授業が揃っています。
製菓本科では、商品企画に必要な企画力を養える「商品企画ゼミ」が選択可能。
スイーツ科にも即戦力を身につけるために商品をゼロから企画、実用化する授業があります。
在学中に自分たちでアイデアを出し合い、チームで商品化する工程は、将来につながる貴重な経験となるでしょう。
「食品メーカーで商品開発に携わりたい」という人は、ぜひ本校でプロさながらの仕事を学ぶことをおすすめします。
パティシエを目指すなら神戸製菓専門学校で学びませんか?
パティシエや和菓子職人、カフェオーナーなどを目指したいのであれば、神戸の中心・三宮駅から徒歩10分のところにある神戸製菓専門学校がおすすめです。
製菓本科(昼2年制)では、在学中に国家資格「製菓衛生師」の取得を目指すことができ、卒業後は国家検定「菓子製造技能士2級」の受験資格も得られます。
なお、国家資格「製菓衛生師」の合格率は2年連続100%です。




スイーツ科(昼1年制)では、1年間の90%以上が実習・演習で毎日実習があり、スイーツの基礎のみならず応用まで身につけることが可能です。